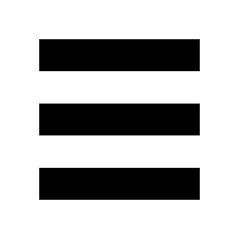九谷焼について
≡
九谷焼は石川県南部で焼き継がれている焼物の総称です。
江戸時代前期の「古九谷」と百年余の中絶の後に江戸後期の 「再興九谷から現代九谷」と続いています。
江戸時代前期の「古九谷」と百年余の中絶の後に江戸後期の 「再興九谷から現代九谷」と続いています。
1655年(355年前)
「古九谷」はここ山代から20キロほど離れた九谷村に前田百万石の支藩である大聖寺藩(現在の加賀市大聖寺)の初代藩主利治が全長34mの窯を築かせ作り始めたものです。もともと、加賀百万石の前田家は中国の景徳鎮製の色絵五彩「万暦赤絵」等を色々求めていて色絵磁器に関心がありました。その上大聖寺藩主利治の夫人は佐賀鍋島藩主の孫娘に当たり前田家への進物として有田焼が度々贈られたりで、色絵磁器の先進地の肥前(有田、鍋島家)とはたいへん親密な関係にありました。藩の金山がある九谷村で、陶石が取れることが分り此処に肥前の様式を伝える窯が築かれました。
この窯で作られた九谷焼は色絵(白地に紺、黄色、緑、紫、赤などで描いたもの)と青手(素地を塗り埋め赤以外の3色、4色で描く)の画法がありました。
形状や意匠は色々ですが、前田藩らしい重厚華麗な絵付がされています。
此処で約50年間ほど磁器が焼かれ、その後断絶しましたが、三上次男氏らの調査、測定により、廃絶時代は熱残留磁器方位測定では1688年+−1704年になっています。
1655年に始まり約50年後の1705年頃に廃絶との伝承は、科学的測定との一致が見られます。(この時期に作られたと考えられる焼物は、「古九谷」と称されます。)
1806年
加賀藩が京や肥前から購入する陶磁器は、36〜37万枚に達したので藩金の流出を防ぐため、京都の名工 青木木米を招き春日山窯を開きましたが木米は2年余で帰京しました。
1811年
小松の若杉窯では染付が多い伊万里風を沢山焼き、陶磁器の殖産計画に成功しました。 小野窯、民山窯等も、赤絵などを描きましたが、古九谷風なものは特に意図されませんでした。
1824年
再興九谷というのは大聖寺藩の町年寄の吉田屋(豊田伝衛門)は72歳の時、他ならぬ九谷焼を再興するために巨費を投じ山中の九谷古窯に隣接して窯を再建しました。しかし九谷村では不便なため約1年後に ここ山代に窯を移しました。古九谷の再興を願って始めた吉田屋窯は青手古九谷の手法を受け継ぎながら独自の軽快な透明感のある作風を作り、再興九谷の中でも最も評価の高いものとされます。
1832年
吉田屋窯を継いだ宮本屋は、絵付の飯田屋八郎右衛門により、赤絵細描を完成しました。様々な変転はありましたが、この吉田屋が作った窯は昭和まで使われ続け現在は「窯跡展示館」として様々な作品と共に皆様にご覧頂いております。 先頃九谷村の「九谷古窯跡」と此処山代の「窯跡展示館」は“国指定の史跡”に指定されました。
1841年
地以外の諸窯の代表としての寺井町の九谷庄三は、洋絵の具を用いて豪華な彩色金襴手を生み出して一世を風靡し、今でも九谷焼の代表的なイメージになっています。
1915年
北大路魯山人は山代の須田菁華窯で染付や赤絵を試み、焼物に興味を持たれ、その後、鎌倉に窯を築き沢山の九谷の器も作りました。 三越や高島屋での魯山人の器展の催しの折に私共の工房では、魯山人写しを依頼され、今日でも色々写しを創っております。
1936年
陶芸家・富本健吉氏が加賀市の北出塔次郎氏の処に来られ、色絵小紋に優れた業績を残され、そのモダンな小紋の新鮮さは現代の作家に影響を与えています。 現在まで この山代近辺では古九谷、吉田屋手の流れを継承しながら、さらに新しい現代的な九谷焼を創っている工房や優れた個人作家が多い土地柄です。
「古九谷」はここ山代から20キロほど離れた九谷村に前田百万石の支藩である大聖寺藩(現在の加賀市大聖寺)の初代藩主利治が全長34mの窯を築かせ作り始めたものです。もともと、加賀百万石の前田家は中国の景徳鎮製の色絵五彩「万暦赤絵」等を色々求めていて色絵磁器に関心がありました。その上大聖寺藩主利治の夫人は佐賀鍋島藩主の孫娘に当たり前田家への進物として有田焼が度々贈られたりで、色絵磁器の先進地の肥前(有田、鍋島家)とはたいへん親密な関係にありました。藩の金山がある九谷村で、陶石が取れることが分り此処に肥前の様式を伝える窯が築かれました。
この窯で作られた九谷焼は色絵(白地に紺、黄色、緑、紫、赤などで描いたもの)と青手(素地を塗り埋め赤以外の3色、4色で描く)の画法がありました。
形状や意匠は色々ですが、前田藩らしい重厚華麗な絵付がされています。
此処で約50年間ほど磁器が焼かれ、その後断絶しましたが、三上次男氏らの調査、測定により、廃絶時代は熱残留磁器方位測定では1688年+−1704年になっています。
1655年に始まり約50年後の1705年頃に廃絶との伝承は、科学的測定との一致が見られます。(この時期に作られたと考えられる焼物は、「古九谷」と称されます。)
1806年
加賀藩が京や肥前から購入する陶磁器は、36〜37万枚に達したので藩金の流出を防ぐため、京都の名工 青木木米を招き春日山窯を開きましたが木米は2年余で帰京しました。
1811年
小松の若杉窯では染付が多い伊万里風を沢山焼き、陶磁器の殖産計画に成功しました。 小野窯、民山窯等も、赤絵などを描きましたが、古九谷風なものは特に意図されませんでした。
1824年
再興九谷というのは大聖寺藩の町年寄の吉田屋(豊田伝衛門)は72歳の時、他ならぬ九谷焼を再興するために巨費を投じ山中の九谷古窯に隣接して窯を再建しました。しかし九谷村では不便なため約1年後に ここ山代に窯を移しました。古九谷の再興を願って始めた吉田屋窯は青手古九谷の手法を受け継ぎながら独自の軽快な透明感のある作風を作り、再興九谷の中でも最も評価の高いものとされます。
1832年
吉田屋窯を継いだ宮本屋は、絵付の飯田屋八郎右衛門により、赤絵細描を完成しました。様々な変転はありましたが、この吉田屋が作った窯は昭和まで使われ続け現在は「窯跡展示館」として様々な作品と共に皆様にご覧頂いております。 先頃九谷村の「九谷古窯跡」と此処山代の「窯跡展示館」は“国指定の史跡”に指定されました。
1841年
地以外の諸窯の代表としての寺井町の九谷庄三は、洋絵の具を用いて豪華な彩色金襴手を生み出して一世を風靡し、今でも九谷焼の代表的なイメージになっています。
1915年
北大路魯山人は山代の須田菁華窯で染付や赤絵を試み、焼物に興味を持たれ、その後、鎌倉に窯を築き沢山の九谷の器も作りました。 三越や高島屋での魯山人の器展の催しの折に私共の工房では、魯山人写しを依頼され、今日でも色々写しを創っております。
1936年
陶芸家・富本健吉氏が加賀市の北出塔次郎氏の処に来られ、色絵小紋に優れた業績を残され、そのモダンな小紋の新鮮さは現代の作家に影響を与えています。 現在まで この山代近辺では古九谷、吉田屋手の流れを継承しながら、さらに新しい現代的な九谷焼を創っている工房や優れた個人作家が多い土地柄です。
トップ
お知らせ
会社紹介
アクセス
美陶園のこと
商品紹介
オーダー品
お客様の声
お取扱い店
ブログ
オンラインショップ
よくあるご質問
九谷焼について
加賀温泉のおすすめ
ツーリストの皆様へ
お取引先様
関連リンク
お問い合せ
サイトマップ
検索
■
MENU
 検 索
検 索
© 2020 KUTANI BITOUEN All Rights Reserved.